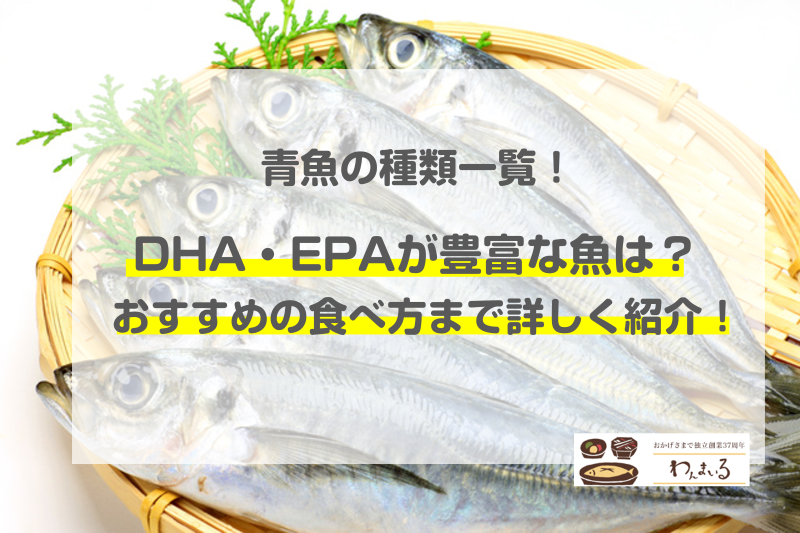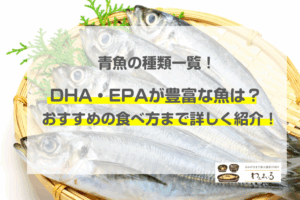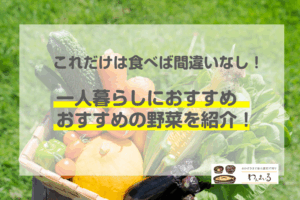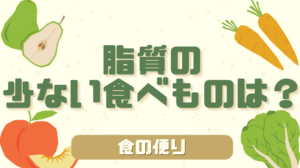運営会社:株式会社ファミリーネットワークシステムズ
住所:〒530-0051大阪市北区太融寺町8-8日清ビル5F
法人番号:6120001092424
公式HP:https://e-fns.co.jp
オリゴ糖は適正量を守れば危険ではなく、むしろ腸内環境改善に役立つ有益な成分
一般的な摂取量は15~18g程度を守れば危険性はありません。
購入時は添加物や人口甘味料が含まれていないか確認するようにしましょう。
オリゴ糖は健康食品として注目を集めていますが、インターネット上では「危険」という情報も見かけることがあります。
実際のところ、オリゴ糖は本当に危険なのでしょうか?
本記事では、オリゴ糖の安全性について科学的根拠をもとに解説します。
また、適切な摂取量やメリット・デメリット、選び方のポイントまで幅広くご紹介しますので、これからオリゴ糖を安全に活用したいとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
オリゴ糖は適正量を摂取する分には危険ではない

オリゴ糖は、適切な量を守って摂取すれば安全な食品成分です。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所の「健康食品の安全性・有効性情報」によると、オリゴ糖は一般的な摂取量であれば健康への悪影響は認められていません。
実際に、オリゴ糖は私たちの身近な食品にも含まれています。
大豆、ごぼう、玉ねぎ、バナナなどの野菜や果物に天然に存在する成分であり、これらの食品を日常的に食べている私たちにとって、オリゴ糖は決して危険な物質ではないのです。
重要なのは「適正量」を守ることです。どんなに体に良いとされる成分でも、過剰に摂取すれば何らかの不調を引き起こす可能性があります。
オリゴ糖も例外ではなく、一度に大量に摂取すると消化器系に負担をかけることがあるため、推奨される摂取量を守ることが大切です。
参照:クルルのおいしいオリゴ糖 – 「 健康食品 」の安全性・有効性情報
安全性は国内の機関でも確認済み
オリゴ糖の安全性については、国内の公的機関でも確認されています。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所のデータベースでは、フラクトオリゴ糖をはじめとする各種オリゴ糖について詳細な安全性情報が公開されています。
フラクトオリゴ糖はタマネギ、ゴボウなどに多く含まれ、それぞれ乾燥中に25.0%、16.7%含まれる。その他ネギ、ニンニク、バナナ、ライムギなど数多くの食品にも少量ではあるが含まれている。このことから、通常の食品に多く含まれ、長期間にわたり食されていることから、食経験上安全といえる。
上記ページの情報によると、通常の食事から摂取される量や、健康食品として推奨される量(1日あたり2~10g程度)であれば、健康な成人において安全性に問題はないとされています。
また、長期間の摂取試験でも、適切な量であれば有害事象は報告されていないことが確認されています。
さらに、オリゴ糖は「特定保健用食品(トクホ)」の成分としても数の多くの食品で認可されています。
トクホは、有効性や安全性について国の審査を受けた食品であり、この認可を受けているということは、オリゴ糖の安全性が公的に認められている証拠といえるでしょう。
なぜオリゴ糖は「危険」と言われるのか?
では、オリゴ糖自体は安全な成分であるにもかかわらず、なぜ「危険」という情報が広まっているのでしょうか。
その背景には、いくつかの誤解や個人差による体験が関係しているようです。
まず、オリゴ糖を含む製品の中には、添加物や人工甘味料が含まれているものがあります。
これらの添加物に対する不安が、オリゴ糖そのものへの不信感につながっている可能性があるでしょう。
また、体質によってはオリゴ糖を摂取することで消化器症状が現れる人もいます。
このような個人的な体験が、SNSやブログなどで「オリゴ糖は危険」という情報として拡散されることもあるでしょう。
さらに、「天然成分だから安全」という思い込みから、過剰摂取してしまい、その結果として不調を経験した人の声が「危険」という評価につながっているケースも考えられます。
加工品に含まれる添加物のリスク
市販されているオリゴ糖製品の中には、純粋なオリゴ糖だけでなく、様々な添加物が含まれているものがあります。
例えば、保存料、着色料、香料、人工甘味料などが添加されている製品も少なくありません。
これらの添加物は、それぞれ安全性が確認されているものですが、人によってはアレルギー反応を引き起こしたり、体質に合わなかったりすることがあります。
特に、人工甘味料については、摂取後に頭痛や胃腸の不調を訴える人もいます。
※ただし、一部の敏感な人が症状を訴えているにとどまり、一般的な副作用ではないので注意が必要です
そのため、オリゴ糖製品を選ぶ際は、成分表示をよく確認することが重要です。
できるだけシンプルな成分構成で、添加物の少ない製品を選ぶことで、これらのリスクを回避することができるでしょう。
純度の高いオリゴ糖製品を選べば、添加物による不調を心配する必要はありません。
参考:国立医薬品食品衛生研究所
オリゴ糖に使用される添加物一覧表
| 甘味料名 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| ステビア | 天然 | 植物由来、高甘味でカロリーゼロ |
| アスパルテーム | 人工 | 甘味度高いがフェニルケトン尿症の人は注意 |
| アセスルファムK | 人工 | 熱安定性あり、他の甘味料と併用されやすい |
| スクラロース | 人工 | 砂糖に近い味質、安定性が高い |
| ソルビトール | 糖アルコール | 緩下作用あり、低カロリー |
| エリスリトール | 糖アルコール | カロリーゼロ、虫歯になりにくい |
| マルチトール | 糖アルコール | 砂糖の80%程度の甘さ、血糖値への影響少 |
| 添加物名 | 用途 |
|---|---|
| クエン酸 | pH調整、風味付け、防腐効果 |
| 乳酸ナトリウム | 保存性向上 |
| 安息香酸ナトリウム | 微生物抑制(ただし使用基準あり) |
| 添加物名 | 用途 |
|---|---|
| 増粘多糖類(キサンタンガム等) | 粘度調整、安定性確保 |
| ペクチン | 天然由来、ゲル化・安定化 |
体質によっては下痢や腹痛を引き起こすことも
オリゴ糖は「難消化性」という特徴を持っています。
これは、小腸で吸収されずに大腸まで届くという性質を指します。
この性質により、腸内の善玉菌(ビフィズス菌など)のエサとなり、腸内環境の改善に役立つのです。
しかし、この難消化性という特徴が、一部の人にとっては消化器症状の原因となることがあります。
オリゴ糖を大量に摂取すると、大腸内で発酵が過剰に起こり、ガスが発生したり、浸透圧の関係で水分が腸内に引き込まれたりして、腹痛や下痢を引き起こすことがあるのです。
特に、もともと過敏性腸症候群(IBS)などの消化器疾患を持っている人や、腸内環境が乱れている人は、少量のオリゴ糖でも症状が現れやすい傾向があります。
このような体質の人は、ごく少量から始めて、徐々に量を増やしていくなど、慎重に摂取する必要があります。
参考:株式会社パールエース
「自然=安全」とは限らないことへの誤解
オリゴ糖は天然の食品に含まれる成分であることから、「自然なものだから安全」と考える人が多いようです。
しかし、天然成分であっても、摂取量や摂取方法を誤れば、体に悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、キノコや山菜の中には毒性を持つものがありますし、ハーブティーとして親しまれているセントジョーンズワートは、医薬品との相互作用を起こすことが知られています。
つまり、「天然」や「自然」という言葉は、必ずしも「安全」を保証するものではないのです。
オリゴ糖についても同様で、天然由来の成分だからといって無制限に摂取してよいわけではありません。
適切な量を守り、自分の体質に合った摂取方法を見つけることが、安全にオリゴ糖を活用するための重要なポイントとなるでしょう。
参考:eJIM
オリゴ糖を摂取するメリット・デメリット
| オリゴ糖を摂取するメリット | オリゴ糖を摂取するデメリット(注意点) |
|---|---|
| 善玉菌(ビフィズス菌など)の増殖を促す | 過剰摂取で下痢・腹痛・ガスが発生することがある |
| 整腸作用(便秘や下痢の改善)が期待できる | 過敏性腸症候群(IBS)やFODMAPに敏感な体質では不調を招くことがある |
| 血糖値の上昇が緩やかで糖尿病患者にも使いやすい | 市販品の中には人工甘味料や添加物が含まれている場合がある |
| 砂糖より低カロリーでダイエット中にも適している | 「自然=安全」と誤解して過剰摂取するリスクがある |
オリゴ糖には腸内環境の改善などの健康効果が期待される一方で、これまで解説してきた通り、体質や摂取量によっては不調を招くこともあります。
具体的なメリット・デメリットについては、以下の項目で詳しく解説します。
オリゴ糖の代表的なメリット
オリゴ糖の最も重要なメリットは、腸内環境の改善効果です。
オリゴ糖は、腸内のビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌のエサとなり、これらの菌の増殖を促進します。
善玉菌が増えることで、腸内のpHが下がり、悪玉菌の増殖が抑制されます。
この腸内環境の改善により、便秘の解消や下痢の改善といった整腸作用が期待できます。
また、腸内環境が整うことで、免疫機能の向上、アレルギー症状の緩和、肌荒れの改善など、全身の健康にも良い影響を与えることが研究で明らかになっています。
さらに、オリゴ糖は血糖値への影響が少ないという特徴があります。
通常の砂糖と比較して、血糖値の上昇が緩やかであるため、糖尿病の方や血糖値が気になる方でも、医師の指導のもとで摂取することができるでしょう。
カロリーも砂糖の約半分程度と低く、ダイエット中の方にも適しています。
参考:特定保健用食品
デメリットとして気をつけたい点
オリゴ糖のデメリットとして最も注意すべきは、先ほども解説した通り、過剰摂取による消化器症状です。
一度に大量のオリゴ糖を摂取すると、腹痛、下痢、腹部膨満感、ガスの増加などの症状が現れることがあります。
これは、オリゴ糖が大腸で急激に発酵することが原因です。
また、体質によっては少量でも症状が現れる人もいます。
特に、過敏性腸症候群(IBS)の方や、FODMAP(フォドマップ)と総称される発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオールといった糖類に敏感な体質の方は、オリゴ糖の摂取に注意が必要です。
さらに、オリゴ糖製品の中には、前述のように添加物が含まれているものもあります。
これらの添加物によるアレルギーや体調不良のリスクも考慮する必要があるでしょう。
また、オリゴ糖は甘味料としての効果もありますが、砂糖ほどの甘さはないため、物足りなく感じて過剰に使用してしまう可能性もあります。
参考:胃と大腸の内視鏡ナビ
1日にどのくらい摂取するのが適切?

オリゴ糖の適切な摂取量は、個人の体質や目的によって異なりますが、一般的な目安となる推奨量があります。
適切な量を守ることで、オリゴ糖のメリットを最大限に活かしながら、デメリットを避けることができます。
初めてオリゴ糖を摂取する場合は、少量から始めることが重要です。
体の反応を見ながら、徐々に量を増やしていくことで、自分に合った適量を見つけることができます。
また、オリゴ糖は一度に大量に摂取するよりも、1日の中で数回に分けて摂取する方が、消化器への負担が少なく、効果も得やすいとされています。
朝食時、昼食時、夕食時など、食事と一緒に摂取することがおすすめです。
一般的な推奨摂取量は15〜18g程度
オリゴ糖の一般的な推奨摂取量は、1日あたり2~18g程度とされています。
この量は、腸内環境の改善効果が期待でき、かつ消化器症状のリスクが低い範囲として設定されています。
具体的には、初めてオリゴ糖を摂取する場合は、1日2~10g程度から始めることをおすすめします。
これは小さじ1杯弱に相当する量です。1週間程度この量で様子を見て、特に問題がなければ徐々に増やしていくとよいでしょう。
最終的には、1日15~18g程度まで増やすことができますが、この量に達するまでには数週間から1ヶ月程度かけることが望ましいでしょう。
急激に摂取量を増やすと、腸内環境の変化に体が対応できず、不調を引き起こす可能性があります。
体質や目的に合わせて調整を
オリゴ糖の適切な摂取量は、個人の体質や摂取目的によって調整する必要があります。
例えば、便秘の改善を目的とする場合は、比較的多めの15~18g程度が効果的とされています。
一方、腸内環境の維持を目的とする場合は、2~10g程度でも十分な効果が期待できるでしょう。
消化器系が敏感な方や、過敏性腸症候群(IBS)の方は、通常の推奨量よりも少ない量から始める必要があります。
1日1~2g程度から始めて、体調を見ながら慎重に量を調整していきましょう。
場合によっては、5g以下の少量でも十分な効果が得られることもあります。
また、年齢によっても適切な摂取量は異なります。
高齢者の場合は消化機能が低下していることがあるため、若い人よりも少ない量から始めることが推奨されています。
子どもの場合も、体重に応じて摂取量を調整する必要があるでしょう。
いずれの場合も、医師や栄養士に相談しながら、適切な量を決めることが大切です。
オリゴ糖には種類があることを知っておこう
| 代表的なオリゴ糖 | 含まれている食品 |
|---|---|
| フラクトオリゴ糖 | 玉ねぎ、ごぼう、バナナなど |
| ガラクトオリゴ糖 | 牛乳、母乳など |
| 大豆オリゴ糖 | 大豆 |
| イソマルトオリゴ糖 | はちみつ、味噌、醤油 |
オリゴ糖と一口に言っても、実は様々な種類があります。
それぞれに特徴があり、効果や適した用途も異なります。
自分の目的や体質に合ったオリゴ糖を選ぶことで、より効果的に活用することができます。
オリゴ糖の種類は、原料や製造方法によって分類されます。
代表的なものには、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、大豆オリゴ糖、イソマルトオリゴ糖などがあります。
これらのオリゴ糖は、甘味の強さ、カロリー、腸内での発酵速度、耐熱性などが異なります。
料理に使用する場合は耐熱性の高いものを、カロリーを抑えたい場合は低カロリーのものを選ぶなど、用途に応じて使い分けることが重要となります。
参考:厚生労働省
代表的なオリゴ糖の種類一覧
フラクトオリゴ糖は、最も一般的なオリゴ糖の一つです。
砂糖の約30~60%の甘さを持ち、玉ねぎ、ごぼう、バナナなどに天然に含まれています。
ビフィズス菌の増殖効果が高く、整腸作用に優れているのが特徴です。
熱に強いため、料理にも使いやすいオリゴ糖といえるでしょう。
ガラクトオリゴ糖は、乳糖を原料として作られるオリゴ糖です。
母乳にも含まれており、赤ちゃんの腸内環境を整える働きがあります。甘味は砂糖の約20~40%程度で、さっぱりとした味わいが特徴です。
ビフィズス菌の増殖効果に加え、カルシウムの吸収を促進する効果も期待できます。
大豆オリゴ糖は、大豆から抽出されるオリゴ糖で、ラフィノースやスタキオースなどが含まれています。
甘味は砂糖の約70%程度と比較的強く、コクのある味わいが特徴です。
イソマルトオリゴ糖は、でんぷんを原料として作られ、はちみつや味噌、醤油などにも含まれています。
熱や酸に強く、料理での使用に適しています。
糖尿病の方でもオリゴ糖は摂取できる?
糖尿病の方にとって、糖質の摂取は血糖値管理の観点から慎重になる必要があります。
オリゴ糖は砂糖と比較して血糖値への影響が少ないとされていますが、糖尿病の方が摂取する場合には注意が必要です。
オリゴ糖は難消化性の性質を持つため、小腸でほとんど吸収されません。
そのため、血糖値の急激な上昇を引き起こしにくいという特徴があります。
しかし、完全に血糖値に影響しないわけではないのです。
糖尿病の方がオリゴ糖を摂取する場合は、必ず主治医に相談し、血糖値の変動を確認しながら、適切な量を決めることが重要です。
自己判断での摂取は避け、医療専門家の指導のもとで安全に活用することをおすすめします。
血糖値に与える影響は低めだが注意は必要
| 甘味料の種類 | GI値(グリセミック指数) |
|---|---|
| 砂糖(ショ糖) | 65〜70 |
| オリゴ糖 | 10〜35 |
オリゴ糖は、通常の砂糖(ショ糖)と比較して血糖値への影響が少ないことが知られています。これは、オリゴ糖が難消化性であり、小腸でほとんど吸収されないためです。
一般的に、オリゴ糖のGI値(グリセミック指数)は10~35程度と、砂糖の65~70と比較して大幅に低い値を示します。
しかし、オリゴ糖の種類によっては、一部が消化・吸収される可能性があります。
例えば、イソマルトオリゴ糖は他のオリゴ糖と比較して消化されやすい傾向があるのです。
また、市販のオリゴ糖製品の中には、純度が低く、他の糖類が混ざっているものもあるため注意が必要です。
糖尿病の方がオリゴ糖を摂取する場合は、血糖測定器を使用して、摂取前後の血糖値の変化を確認することをおすすめします。
個人差があるため、自分の体がオリゴ糖にどのように反応するかを把握することが、安全な摂取につながります。
医師の指導のもとでの摂取が望ましい
糖尿病の方がオリゴ糖を摂取する場合は、必ず主治医や管理栄養士に相談することが重要です。
糖尿病の重症度、使用している薬剤、合併症の有無などによって、オリゴ糖の摂取が適切かどうかは異なります。
医師は、患者さんの状態を総合的に判断し、オリゴ糖の摂取が可能かどうか、可能な場合はどの程度の量が適切かをアドバイスしてくれます。
また、血糖コントロールの状況を見ながら、摂取量の調整も行ってくれるでしょう。
インスリンや経口血糖降下薬を使用している場合、オリゴ糖の摂取が血糖値やインスリン分泌に間接的な影響を及ぼす可能性があります。
薬そのものの効果に直接影響を与える明確な根拠はありませんが、治療中の方は医師に相談のうえで摂取するのが安全です。
医療専門家の指導のもとで、体調や治療内容に応じてオリゴ糖を活用することが大切です。
体に良いオリゴ糖を選ぶためのチェックポイント
- オリゴ糖の純度が明記されている
- 保存料や香料、人工甘味料が含まれていない
- 「プレバイオティクス」や「トクホ」の表示がある
- メーカーや販売元の信頼性が高い
- 継続的に摂取しやすい価格と量である
市場には様々なオリゴ糖製品が販売されていますが、品質や成分には大きな差があります。
体に良いオリゴ糖を選ぶためには、いくつかの重要なポイントをチェックする必要があります。
まず確認すべきは、オリゴ糖の純度です。
純度の高い製品ほど、オリゴ糖本来の効果を期待できます。
次に、添加物の有無を確認しましょう。
余計な添加物が含まれていない、シンプルな成分構成の製品がおすすめです。
また、製造方法や原料の品質、メーカーの信頼性なども重要な判断基準となります。
価格だけで選ぶのではなく、品質と安全性を重視して選ぶことが、長期的な健康維持につながります。
添加物・人工甘味料が含まれていないか確認
オリゴ糖製品を選ぶ際、最も重要なチェックポイントの一つが添加物の有無です。
純粋なオリゴ糖製品であれば、原材料名にはオリゴ糖の種類(フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖など)のみが記載されているはずです。
しかし、市販製品の中には、保存料、着色料、香料、増粘剤などの添加物が含まれているものがあります。
また、甘味を増すために人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムカリウムなど)が添加されている製品も存在します。
これらの添加物は、それぞれ安全性が確認されているものですが、体質によってはアレルギーや不調の原因となることがあります。
特に、毎日継続的に摂取することを考えると、できるだけ添加物の少ない、純粋なオリゴ糖製品を選ぶことをおすすめします。
成分表示をしっかりと確認し、シンプルな成分構成の製品を選びましょう。
参考:POSSIN
「プレバイオティクス」表示のある製品がおすすめ
プレバイオティクスとは、
有用細菌の増殖を促進、あるいは有害菌を抑制することによって、宿主の健康に有利に働く非消化性食品成分
と定義されています。
つまり、人間の体では消化されずに腸まで届き、善玉菌(ビフィズス菌など)のエサとなって腸内環境を整える働きを持つ食品成分を指します。
オリゴ糖は、このプレバイオティクスの代表的な成分のひとつです。とくにフラクトオリゴ糖は、
1982年、株式会社明治(以下「明治」という)
は「フラクトオリゴ糖が胃酸やヒト小腸内酵素によ
り分解および消化されることなく大腸に到達し(難
消化性)、乳酸菌やビフィズス菌など善玉菌の餌に
なり、腸内フローラを改善する」という知見を世界
で初めて発見した。
と書かれている通り、腸内の有用菌を選択的に増やす効果が期待されています。
実際に摂取することで、便通の改善や腸内環境の維持に寄与することが報告されています。
また、特定保健用食品(トクホ)の認可を受けたオリゴ糖製品も存在し、これらは有効性および安全性について国の科学的審査を経て表示が認められたものです。
製品選びに迷った際は、こうした表示も一つの判断材料となるでしょう。
まとめ|オリゴ糖の正しい知識で健康的に活用しよう
オリゴ糖は、適切に摂取すれば腸内環境の改善をはじめとする様々な健康効果が期待できる有益な成分です。
「危険」という情報に惑わされることなく、科学的根拠に基づいた正しい知識を持つことが大切です。
重要なのは、自分の体質に合った種類と量を見つけ、質の良い製品を選ぶことです。
初めは少量から始めて徐々に増やし、体調の変化を観察しながら、オリゴ糖を健康維持に役立てていきましょう。
医師や栄養士などの専門家のアドバイスも参考にしながら、オリゴ糖を上手に活用することで、より健康的な生活を送ることができるはずです。