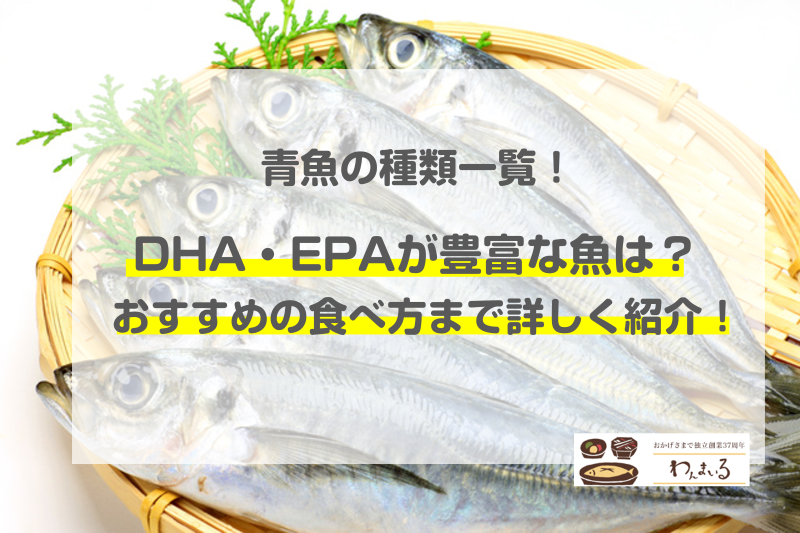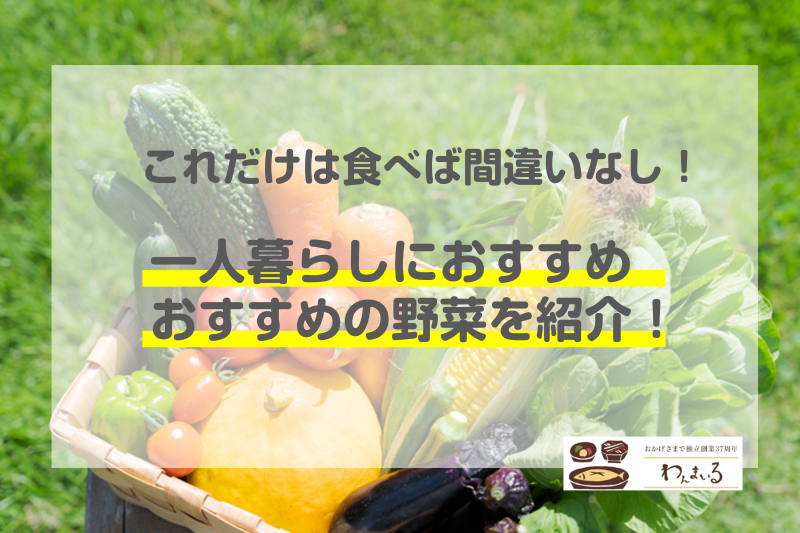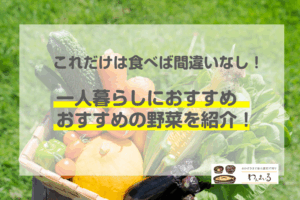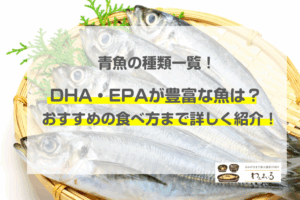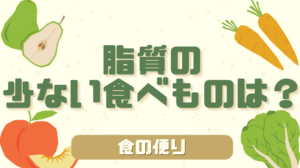運営会社:株式会社ファミリーネットワークシステムズ
住所:〒530-0051大阪市北区太融寺町8-8日清ビル5F
法人番号:6120001092424
公式HP:https://e-fns.co.jp
一人暮らしを始めると、何を食べたらいいのか悩むことも多いですね。
栄養バランスや手軽さを重視しながら、毎日の食事に取り入れやすいおすすめ野菜をご紹介します。
これさえ押さえれば、健康的な食生活がぐっと楽になります。
【結論!】これだけ食べておけば大丈夫という野菜は存在しない
野菜は健康維持に大切な食材ですが、「これだけ食べておかば大丈夫」と考えるのは誤りです。
どの野菜も栄養素が異なるため、一種類だけ大量に摂取しても不十分です。
野菜にはビタミンやミネラルが含まれていますが、タンパク質や脂質など他の栄養素も必要です。
バランスの取れた食事を心掛けることが重要になります。
特定の野菜だけを過剰に摂ることも健康リスクとなる可能性があります。
健康維持には多様な野菜を少しずつ摂ることが効果的です。
つまり、「これだけで大丈夫」は誤解であり、偏った食事は避けるべきです。
日々の食事に野菜だけでなく、魚や肉、穀物も取り入れることが理想です。全体のバランスを意識して、健康的な食生活を目指しましょう
野菜に主に含まれる栄養素
野菜は栄養豊富とされていますが、摂れる栄養素は限られています。肉や魚にも同じことが言えます。
例えば、肉や魚にはタンパク質が多く含まれていますが、野菜はそれほど多くありません。
その代わりに、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富です。
野菜に含まれる栄養素には、ビタミンCやD、K、カルシウムやカリウム、鉄や亜鉛、水溶性と不溶性の食物繊維、アミノ酸、 β-カロテンなどがあります。
これらは全て健康維持に必要な栄養素です。
したがって、バランス良くさまざまな栄養素を摂るために、意識して野菜を取り入れることが大切です。
これだけ食べておけば大丈夫?一人暮らしにおすすめ野菜5選!
一人暮らしにおすすめな野菜は次の5つです。
基本的にバランス良く摂取をすることが、前提ですが下記で紹介する野菜は特に栄養素が高いので一人暮らしの方は特に積極的に摂取したほうが良い野菜です。
- トマト
- キャベツ
- 玉ねぎ
- ほうれん草
- もやし
以下では上記の野菜のおすすめ度や栄養素などを紹介していきます。
トマト

| おすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 主な栄養素 | ビタミンC、ビタミンA、カリウム、食物繊維、リコピンなど |
| コスパ | 335円(kg)※1 |
| 消費のしやすさ | ★★★★★ |
| 体への効果 | リコピンは抗酸化作用があり、生活習慣病の予防や老化抑制に効果があるとされています。また、ビタミンCは美肌効果や風邪予防に役立ち、カリウムは高血圧予防に効果があります。 |
キャベツ

| おすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 主な栄養素 | ビタミンC、ビタミンK、葉酸、カリウム、食物繊維、ビタミンU(キャベジン)など |
| コスパ | 74円(kg)※1 |
| 消費のしやすさ | ★★★★★ |
| 体への効果 | 特にビタミンUは胃腸の粘膜を保護する働きがあり、胃腸薬の成分にも使われています。また、食物繊維は便秘解消や腸内環境改善に役立ちます。 |
玉ねぎ

| おすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 主な栄養素 | ビタミンC、ビタミンB群、カリウム、食物繊維など |
| コスパ | 153(kg)※1 |
| 消費のしやすさ | ★★★★★ |
| 体への効果 | 血液サラサラ効果や抗酸化作用、腸内環境改善などの効果が期待できます。 |
ほうれん草

| おすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 主な栄養素 | ビタミンA、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、鉄、カリウム、カルシウム、食物繊維など |
| コスパ | 495円(kg)※1 |
| 消費のしやすさ | ★★★★★ |
| 体への効果 | 免疫力向上、貧血予防、便秘解消、高血圧予防、美肌効果などが期待できます。 |
もやし

| おすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 主な栄養素 | ビタミンC、ビタミンB群、カリウム、食物繊維など |
| コスパ | ★★★★★※1 |
| 消費のしやすさ | ★★★★★ |
| 体への効果 | 便秘や糖尿病、大腸ガンといった生活習慣病を予防・改善する働きがあります。 ビタミンCは水に溶けるビタミンで、血管を強化したり鉄分の吸収を促進する働きがあります。 その他コレステロールの低下やガン、動脈硬化を予防する効果があります。 カゼの予防にも最適です。 |
※1コスパに関する評価は農林水産省の毎日の卸売価格を参考に決定・制作を行っています。
野菜の各栄養分別含有量トップ10
野菜の各栄養分別含有量トップ10は以下の通りです。
以下では上記の各野菜にどれくらいの栄養素が含まれているのかを紹介していきます。
ビタミンB1

| 野菜 | ビタミンB1含有量(mg/100g) |
|---|---|
| グリンピース | 0.39mg |
| えだまめ | 0.31mg |
| そらまめ | 0.30mg |
| にんにく | 0.19mg |
| 芽キャベツ | 0.19mg |
| モロヘイヤ | 0.18mg |
| ブロッコリー | 0.17mg |
| あさつき | 0.15mg |
| さやえんどう | 0.15mg |
| スイートコーン | 0.15mg |
ビタミンB2

| 野菜名 | 含有量 |
|---|---|
| わらび | 1.09mg |
| モロヘイヤ | 0.42mg |
| とうがらし | 0.36mg |
| しそ | 0.34mg |
| マッシュルーム | 0.29mg |
| なばな | 0.24mg |
| パセリ | 0.24mg |
| ブロッコリー | 0.23mg |
| 芽キャベツ | 0.23mg |
| 生しいたけ(原木) | 0.22mg |
カルシウム

| 野菜名 | 含有量 |
|---|---|
| パセリ | 290mg |
| モロヘイヤ | 260mg |
| しそ | 230mg |
| みずな | 210mg |
| こまつな | 170mg |
| ルッコラ | 170mg |
| つるむらさき | 150mg |
| はくさい(山東菜) | 140mg |
| しゅんぎく | 120mg |
| タアサイ | 120mg |
カリウム

| 野菜名 | 含有量 |
|---|---|
| パセリ | 1,000mg |
| とうがらし | 760mg |
| 食用ゆり | 740mg |
| ほうれんそう | 690mg |
| さといも(セレベス) | 660mg |
| さといも | 640mg |
| みつば(切みつば) | 640mg |
| さといも(やつがしら) | 630mg |
| 芽キャベツ | 610mg |
| くわい | 600mg |
食物繊維

| 野菜名 | 含有量 |
|---|---|
| らっきょう | 20.7g |
| エシャレット | 11.4g |
| とうがらし | 10.3g |
| ばれいしょ | 9.8g |
| グリンピース | 7.7g |
| しそ | 7.3g |
| パセリ | 6.8g |
| たで | 6.3g |
| にんにく | 6.2g |
| モロヘイヤ | 5.9g |
β-カロテン

| 野菜名 | 含有量 |
|---|---|
| しそ | 11,000μg |
| モロヘイヤ | 10,000μg |
| にんじん | 8,600μg |
| とうがらし | 7,700μg |
| パセリ | 7,400μg |
| にんじん | 5,000μg |
| たで | 4,900μg |
| しゅんぎく | 4,500μg |
| ほうれんそう | 4,200μg |
| かぼちゃ | 4,000μg |
ビタミンC

| 野菜名 | 含有量 |
|---|---|
| ピーマン(トマピー) | 200mg |
| 赤ピーマン(パプリカ) | 170mg |
| 芽キャベツ | 160mg |
| 黄ピーマン(パプリカ) | 150mg |
| オレンジピーマン(パプリカ) | 150mg |
| ブロッコリー | 140mg |
| とうがらし | 120mg |
| パセリ | 120mg |
| なばな | 110mg |
| カリフラワー | 81mg |
※記載内容は各野菜の100gあたりの数値
※参考サイト:農畜産業振興機構
※の情報
食べても意味がない!?栄養素があまりない野菜ランキングTOP5
下記では栄養素があまり含まれていない野菜を紹介します。
食物繊維・ビタミンを摂取を目的として野菜を食べる際は効率が悪いので栄養価が高い野菜を選ぶことをおすすめします。
1位:レタス

| 成分名 | 含有量 |
|---|---|
| カルシウム | 19mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| カリウム | 200mg |
| β-カロテン当量 | 240µg |
| ビタミンB1 | 0.05mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンC | 5mg |
| 食物繊維 | 1.1g |
2位:きゅうり

| 成分名 | 含有量 |
|---|---|
| カルシウム | 26mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| カリウム | 200mg |
| β-カロテン当量 | 330µg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンC | 14mg |
| 食物繊維 | 1.1g |
3位:セロリ

| 成分名 | 含有量 |
|---|---|
| カルシウム | 39mg |
| 鉄 | 0.2mg |
| カリウム | 410mg |
| β-カロテン当量 | 44µg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンC | mg |
| 食物繊維 | 1.5g |
4位:白菜

| 成分名 | 含有量 |
|---|---|
| カルシウム | 43mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| カリウム | 220mg |
| β-カロテン当量 | 99µg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンC | 19mg |
| 食物繊維 | 1.3g |
5位:ナス

| 成分名 | 含有量 |
|---|---|
| カルシウム | 18mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| カリウム | 220mg |
| β-カロテン当量 | 100µg |
| ビタミンB1 | 0.05mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ビタミンC | 4mg |
| 食物繊維 | 2.2g |
※参考サイト:農畜産業振興機構
※の情報
野菜は1日にどのくらい摂取すればよい?
生活習慣病予防の観点から、1日に必要な野菜量は350g以上と推奨されています。
野菜にはさまざまな健康効果があります。
例えば、カリウムが豊富に含まれており、これはナトリウム(食塩)を体外に排出して血圧を下げる働きがあります。
また、ビタミン類も多く含まれており、体内の細胞や組織の酸化を防ぐ抗酸化作用を持っています。
さらに、野菜に豊富に含まれる食物繊維には複数の効果があります。
腸内環境を良好に保つだけでなく、コレステロールの吸収を抑える働きもあるため、生活習慣病予防に役立つでしょう。
摂取する野菜の種類の内訳
毎日の食事で野菜をどのように取り入れればよいのでしょうか。
実は、小鉢や小皿に入った野菜料理1つ分には、約70gの野菜が含まれていると考えられます。
例えば、ほうれん草のお浸し、具だくさん味噌汁、きゅうりとわかめの酢の物などの小鉢1つ、または生野菜のサラダ中皿1つが目安となります。
1日に必要な野菜量(約350g)を摂るためには、このような小鉢を5皿程度食べることで達成できます。
副菜だけでなく、主菜として食べる野菜炒めやポトフ、とんかつに添えられたキャベツなども含めて考えましょう。
これらの料理に含まれる野菜も小鉢に置き換えて、1日の摂取量を確認するとよいでしょう。
緑黄色野菜
緑黄色野菜には主に以下の野菜が該当します。
- アスパラガス
- かぼちゃ
- さやえんどう
- オクラ
- にんじん
- トマト
- ピーマン
- ブロッコリー
- ほうれん草
- サニーレタス
- 大根の葉
- にら
- チンゲンサイ
- 春菊
- しそ
緑黄色野菜とは、β-カロテンを豊富に含む野菜のことです。
具体的には、可食部100gあたりβ-カロテンが600マイクログラム以上含まれるものを指します。
また、β-カロテンの含有量が基準未満でも、トマトやピーマンのように日常的に摂取頻度が高いものは緑黄色野菜として分類されています。
主な緑黄色野菜には、表にもある通りアスパラガス、かぼちゃ、さやえんどう、オクラ、にんじん、トマト、ピーマン、ブロッコリー、ほうれん草、サニーレタス、大根の葉、にら、チンゲンサイ、春菊、しそなどがあります。
これらの野菜はビタミンAの前駆体であるβ-カロテンを多く含み、視力維持や皮膚の健康維持に役立ちます。
淡色野菜
淡色野菜には主に以下の野菜が該当します。
- キャベツ
- 白菜
- レタス
- もやし
- ごぼう
- 大根
- かぶ
- 玉ねぎ
- にんにく
- れんこん
- きゅうり
- なす
- カリフラワー
- トウモロコシ
- セロリ
淡色野菜とは、緑黄色野菜以外の野菜のことで、切った時の断面の色が薄いものを指します。
β-カロテンの含有量は少ないものの、食物繊維やビタミンCなどの栄養素を豊富に含んでいるのが特徴です。
代表的な淡色野菜には、表にもあるキャベツ、白菜、レタス、もやし、ごぼう、大根、かぶ、玉ねぎ、にんにく、れんこん、きゅうり、なす、カリフラワー、トウモロコシ、セロリなどがあります。
これらの野菜は消化を助け、整腸作用があるものも多いため、バランスよく摂取することが大切です。
緑黄色野菜と淡色野菜はそれぞれ異なる栄養素を含んでいますので、両方をバランスよく摂ることで、より多くの栄養素を効率的に摂取することができます。
日常の食事では、彩りよく両方の種類の野菜を取り入れるよう心がけましょう。
一人暮らしで野菜を無駄にしないためにできる工夫
一人暮らしをしていると、料理をする際に野菜を使い切れずに腐らせてしまうことがよくあります。
せっかく栄養価の高い野菜を購入したのに、結局捨ててしまうのはもったいないですよね。食費の節約にもならず、環境にも良くありません。
そこでここでは、一人暮らしの方が野菜を無駄にせず、最後まで美味しく食べきるための工夫をご紹介します。
ちょっとした買い物のコツや保存方法を知るだけで、野菜の廃棄量を大幅に減らすことができますよ。
購入する際は、日持ちが良い野菜を選択する
一人暮らしで野菜を無駄にしないためには、購入する野菜の種類を工夫することが大切です。
例えば、キャベツやじゃがいも、玉ねぎ、にんじん、大根などは比較的日持ちがする野菜なので、一人暮らしの方におすすめです。
これらの野菜は適切に保存すれば、1週間以上新鮮さを保つことができます。
また、購入する際には必要な分だけを買うことを心がけましょう。
スーパーマーケットの中には、野菜を小分けにして販売しているところもあります。
キャベツの半分や、少量のほうれん草など、一人分の調理に合わせた量を選ぶと良いでしょう。
さらに、野菜の鮮度をチェックするのも重要です。
葉物野菜なら葉がしっかりとしていて色鮮やかなもの、根菜類なら固めで傷のないものを選ぶと長持ちします。
購入時点で新鮮な野菜を選ぶことで、家庭での保存期間を延ばすことができます。
冷凍できる野菜は冷凍室で保管する
冷凍保存は、一人暮らしの強い味方です。多くの野菜は下処理をして冷凍することで、長期保存が可能になります。
例えば、ピーマンやパプリカは種を取り除いて細切りにし、ほうれん草は茹でて水気をしっかり絞ってから冷凍しておくと、必要な時に必要な分だけ使うことができます。
冷凍する際はジッパー付きの保存袋や密閉容器を使い、空気をできるだけ抜いて保存するのがコツです。
また、使いやすい量に小分けして冷凍しておくと、解凍のムラがなく、必要な分だけ取り出せて便利です。
特におすすめなのは、みじん切りにした玉ねぎやニンニクの冷凍です。
調理の下準備として時間がかかるこれらの野菜を冷凍しておくと料理の時短になり、少量ずつ使えるので無駄がありません。
冷凍した野菜は炒め物やスープの具材として活用できますので、忙しい一人暮らしの強い味方になってくれます。
各野菜に適した保管方法
野菜の種類によって最適な保存方法が異なります。
例えば、トマトやなすは常温で保存する方が風味を損なわず美味しく食べられます。
ただし、カットしたものは冷蔵庫で保管しましょう。
葉物野菜は水分を保つことが重要です。
レタスやほうれん草は、ペーパータオルで包んでからポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に保存すると長持ちします。
キャベツや白菜は、使う分だけ外側の葉から取り、芯を残したまま保存するとよいでしょう。
根菜類は冷暗所での保存が基本です。
じゃがいもや玉ねぎは、風通しの良い冷暗所に置くと発芽が遅れ、長期保存が可能になります。
ただし、にんじんや大根は乾燥しやすいので、新聞紙などで包んで冷蔵庫で保存するのが適しています。
きのこ類は水分が多いため、紙袋やキッチンペーパーに包んで保存すると良いでしょう。ビニール袋だと蒸れて傷みやすくなります。
また、小分けにして冷凍保存も可能です。
これらの保存方法を知っておくことで、野菜の鮮度を長く保ち、無駄なく使い切ることができます。
一人暮らしでも野菜をたっぷり取り入れた健康的な食生活を送りましょう。
にんじん
にんじんは、多くの家庭で頻繁に使われる野菜ですが、保存の仕方次第で長持ちさせることが可能です。
常温では、夏場を除きおよそ1週間程度持ちます。
直射日光や高温多湿を避け、涼しい暗所に置くのが良いでしょう。
夏の暑い時期は、傷みやすいため冷蔵庫の野菜室へ入れることをおすすめします。
このとき湿気を嫌うため、新聞紙やキッチンペーパーで一本ずつ包み、立てて保存します。
冷蔵保存の場合は、鮮度を保つために葉がついている場合は葉を切り落とします。
葉が残ったままだと、水分を吸ってにんじん自身が乾燥しやすくなるからです。
カットしてしまったにんじんは、ラップに包むか密封できる保存袋に入れて、野菜室で保存します。できるだけ早めに使い切ることもポイントです。
残った部分が空気に触れると劣化が進みやすくなるため、密封状態を保ちましょう。
また、冷凍保存も選択肢の一つです。調理しやすい大きさにカットし、ジッパー付き保存袋に入れて冷凍します。
冷凍したにんじんは、煮物やスープに利用しやすくなります。
ただし、冷凍すると食感が変わるため、生のままの状態で食べるサラダには向きません。
大根
大根は水分が豊富な野菜ですが、適切に管理すれば長持ちさせることができます。
丸ごと1本の大根は、夏以外では常温でもかなり長く保存可能です。
湿気や乾燥を防ぐために、新聞紙に包み、葉を切り落としてから、立てて冷暗所に置きます。
葉つきの場合は、葉の部分から乾燥しやすいため、事前に葉を取り除いておくことがポイントです。
これにより、野菜の呼吸や湿度調整がしやすくなります。
カットした大根については、乾燥を防ぐためにしっかりとラップに包んで保存しましょう。
切り口からの乾燥や劣化を防ぐためです。
冷蔵庫の場合は、密封容器やラップを使うといいでしょう。
そのまま冷凍でき、必要な分だけ解凍して使えます。
ただし冷凍した大根は、水分が膨張して繊維が壊れやすくなるため、サラダには向きません。
煮物やおでん、味噌汁などの温かい料理に使うと、味が染み込みやすくなり調理しやすいです。
トマト
トマトは、熟す過程で硬くなったり傷ついたりしやすい野菜です。
適切な保存方法を知ることで、長く美味しさを保つことができます。
まず、冷蔵保存はおよそ7日から10日間が目安です。
傷みにくくするために、ヘタ側を下にして1個ずつキッチンペーパーに包み、ポリ袋に入れて、野菜室で保存します。
冷やしすぎると甘味が損なわれることもあるため、寒い季節は常温保存も可能ですが、夏場は避けたほうが良いでしょう。
調理の際は、自然解凍せずに直接使うことも可能です。
約5分ほど室温に置けばガクの部分を簡単に外せ、そのままカットできます。
ただし、トマトはヘタの周囲にカビや傷が付くことがあるため、できるだけ早めに食べることをおすすめします。
トマトの保存に関しては、早めに消費することが鮮度を保つポイントです。
特に、傷や変色を見つけた場合は、その部分だけ早めに取り除き、全体の劣化を抑えましょう。
毎日自炊をしない場合はパック野菜を利用するのあり
忙しい日々の中、毎日きちんと野菜を準備するのは大変です。
そこで、パック入りの野菜や冷凍野菜を利用することもおすすめです。
これらは洗うだけで使えるため、時間を節約できますし、鮮度も長持ちします。
また、適切な保存方法と組み合わせることで、無駄を減らしつつ、いつでも新鮮な野菜を摂取できます。
特に、毎日自炊が難しい場合や、忙しい仕事の合間に手軽に野菜を取りたいときには、パック野菜を活用しましょう。
生野菜のサラダや温野菜の調理に便利ですし、多くの商品は既にカット済みで扱いやすいです。
その一方で、野菜の種類や保存期間にこだわり、家庭での保存も心がけると、より安心して野菜を楽しめます。
野菜の栄養を逃さずに食べることができるレシピ
野菜は私たちの健康を支える重要な食材ですが、調理方法によって栄養価が大きく変わることをご存知でしょうか。
茹でると水溶性ビタミンが流出してしまったり、長時間の加熱で栄養素が壊れてしまったりすることがあります。
しかし、適切な調理法を選べば、野菜の栄養を効率よく摂取することができます。
ここでは、野菜の栄養素を逃さず美味しく食べられる3つのレシピをご紹介します。
短時間調理や蒸し調理を活用することで、野菜本来の栄養価を保ちながら、毎日の食卓に取り入れやすい一品に仕上げましょう。
蒸しキャベツナムル
- キャベツ:1/4個(約250g)
- 塩:小さじ1/3
- にんにくのすりおろし:少々
- ごま油:大さじ1
- 白いりごま:大さじ1
- キャベツの芯を切っておき、葉は1枚ずつはがしていく(芯もあとで使う)。
- キャベツをきれいに洗い、芯の部分を薄切りにして耐熱容器に入れておく。
- 葉の部分は手でちぎって耐熱容器にかける。
- 耐熱容器にラップをかけて、レンジ(600w)で4分ほど加熱する。
- レンジに掛けたら粗熱がとれるまで置いておく。
- キャベツの粗熱がとれたら、余分な水分を絞っていく。
- キャベツに塩とにんにくのすりおろしを加えてもみ込んでいく。
- ごま油を加えてもみ込んでいく。
- 最後に白いりごまをかけて完成。
小松菜漬け
- 小松菜:1袋
- 昆布:2g
- 唐辛子:1本
- 塩:小さじ1/2
- 砂糖:小さじ1
- 醤油:小さじ1/2
- 酢:大さじ1
- だしの素:小さじ½
- 小松菜の根を切り落とし、水洗いし水分を拭き取り、茎と葉を切り分ける。
- 茎をジップ袋に入れ、塩を加えて馴染ませ10分おく。
- 昆布を軽く拭き取り、適当な大きさに切り、唐辛子の種を取り除き輪切りにする。
- 小松菜の水分を拭き取り、袋に戻し入れ、小松菜の葉、昆布、唐辛子、酢、砂糖、醤油、だしの素を加えて馴染ませ、空気を抜き口を閉じ冷蔵庫で1時間漬け込み完成。
キャベツナチーズ焼き
- キャベツ:150g
- 卵:2個
- チーズ:30g
- ツナ:1缶
- マヨネーズ:お好みで
- 刻み海苔:お好みで
- 片栗粉:大さじ2
- ほんだし:小さじ1
- サラダ油:小さじ1
- 合わせた材料をよく混ぜて平らにならす。
- フライパンにサラダ油をひいて焼いていく。
- 全体が固まったらチーズとツナを追加して広げる。
- 生地を半分に折ってひっくり返し2分焼く。
- お皿に乗せてマヨネーズと刻み海苔をかけて完成。
まとめ
一人暮らしにぴったりの野菜は、手軽に調理できて栄養価も高いものが多いです。
バランス良く取り入れることで、健康的な食生活を維持できます。
今回紹介した野菜を参考に、バリエーション豊かな食卓を楽しんでください。